地権者らはカヤの外 除去土壌等に関する3億円の「戦略課題研究」
国立環境研究所の研究チームが、先般「県外最終処分における最大濃縮シナリオ」を発表しましたが、その研究(SⅡー9)が3年間で3億円という破格の研究費がついていることが分かりました。
環境省の外局である独立行政法人環境再生保全機構(ERCA)「令和7年度環境研究総合推進費における新規課題の採択について」プレスリリースより
福島県の中間貯蔵施設における除去土壌に関するテーマは、「行政ニーズ」として「推進戦略における重点課題」とされており、年間1億円(3年間3億円)の研究費がついています。
P21-23に詳細
この研究分野はすでに原発事故直後から様々な形で実施されていると見られます。直近では、2022年度から2024年度末までの3年間、国立環境研究所の遠藤和人研究リーダーの下で以下の研究が実施されました。
【ERCA作成】令和4年度環境研究総合推進費における新規課題の採択決定について220228_技術室一部修正(別添資料2)令和4年度戦略的研究開発領域課題(SⅡ-9)の公募方針
上記「公募方針」によると、「中間貯蔵施設周辺地域が融合的に環境再生・環境創生していくための統合的な研究」と題して大きく3つに分けた研究を提示しています。
① 県外最終処分に向けた除去土壌等の減容技術システムのシナリオ評価と2024年度以降の具体的な技術開発を選択する指標など
② 中間貯蔵施設周辺復興地域が調和し、融合的に環境再生するための段階的シナリオとして、里地里山環境を再生させ、脱炭素社会として被災地域のコミュニティを再構築するための将来環境デザインの提示など
③ 県外最終処分および中間貯蔵施設周辺復興地域の将来デザインに関する円滑かつ公正な合意形成に向けて、様々な処分オプションの社会受容性の評価、さらに多元的公正および、環境・社会・経済面を考慮した合意形成フレームワークを立案
「関連するステークホルダーとともにそれを共有」
「ステークホルダーの意向把握と合意形成」
「地域住民等のステークホルダーの意見が重要であることは言を待たない。」
などの耳触りの良い言葉が並んでいますが、中間貯蔵施設の地権者会をはじめとした原発事故被害者・被災者に対する情報提示や合意形成のプロセスなどはまったくなされておらず、一貫して被害者・被災者はカヤの外です。研究成果として体裁のよいものを残すために散りばめた単なる修飾語に過ぎないのではないでしょうか。
被害者・被災者は、このような研究者らの資金獲得のために利用されていると言っても過言ではありません。
この研究成果に基づく県外最終処分における最大濃縮シナリオとして、最終処分の対象物が7億㏃/kg、ドラム25本分との試算が発表されたのですが、この研究成果物を広く公開してほしいとイベントの席で遠藤研究員に伝えたところ、「すでに公表しているのでいつでも提供する」とのことでしたので、後日メールで依頼しましたが、何の返信もありませんでした。
【減容技術開発について】
こちらのスライドは、2017年環境創造センターのオープン記念で国立環境研究所が提示していたポスターそのものです。
環境創造センター展示ポスターより
このポスターでは最終処分対象物は数十億㏃/kgに達することが示されています。次回訪問した際にこのポスターを見せてほしいと依頼したところ、放射性物質の濃度の数値がすべて削除されていました。
原発事故後の放射性物質に関する研究は、事故直後から盛んに行われており、同機構のサイトには2017年からのパンフレットが掲載されています。
これまでの研究採択一覧 採択課題一覧|公募情報|環境研究総合推進費|独立行政法人環境再生保全機構

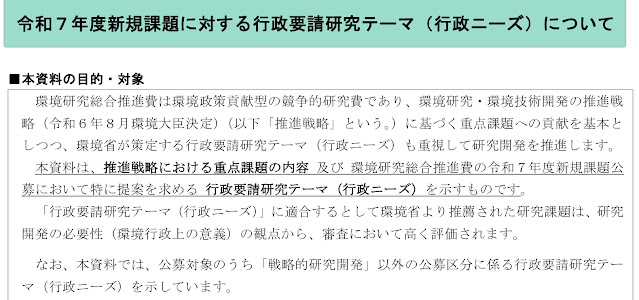









コメント
コメントを投稿