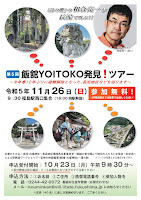4,000ベクレルは「深刻な汚染」 汚染土再利用でセシウムボール再拡散も

環境省側は、2025年度にも8,000ベクレル以下の汚染土再利用を本格化するため、追い込みに入っていると見られます。 8,000ベクレル以下は一般ごみでは通常のごみと同様に「安全」に処理できる基準とされていますが、果たして本当でしょうか。 古典的名著であり脱原発運動の必携である 「放射線被曝の歴史 アメリカ原爆開発から福島原発事故まで」(中川保雄著) によれば、4,000ベクレルであっても深刻な汚染だとされています。 最近の被曝問題の特徴を示す第三の例としてあげなければならないのは、原発周辺地で起きている事柄である。アメリカ、サクラメント市にあるランチョセコ原発は、一九八九年六月に住民投票で閉鎖が決定された。ランチョセコ原発は一九七四年に運転を開始した出力九二万キロワットの加圧水型炉で、決して古いとは言えぬ原発であった。しかしランチョセコは、運転開始から事故続きの札付きの原発であった。事故の多くは蒸気発生器細管の破損であった。ジャーナリズムはほとんど報道しなかったが、その蒸気発生器細管事故によって、放射能汚染は深刻な状態となっていた。たとえば、周辺地の土壌では放射性セシウム濃度は最高で一キログラムあたり四〇〇〇ベクレルにも達していた。(p.236) さらに、汚染土再利用によってセシウムボール(CsMP)が再びまき散らされ、吸入するリスクも見逃せません。 福島原発周辺では、土壌1gあたり最大300個と多く、大気中や海水中に長く浮遊すること、吸入した場合に肺に数十年以上留まるという研究結果が出ています。( ちくりん舎ニュース2023.12.25 p.6) 一元管理が原則なはずの放射能汚染土を、再利用と称して全国へばらまく、しかも何千億円もの税金を使うなど、狂気の沙汰としか言いようがありません。一体誰の発案で、どのような意思決定がなされたのでしょうか。 「世界初のナショナルプロジェクト」とされる汚染土再利用のための「全国民的理解の醸成」の前に、きちんと説明すべきことがなされていないのではないでしょうか。